古今、重症度ステージングの話
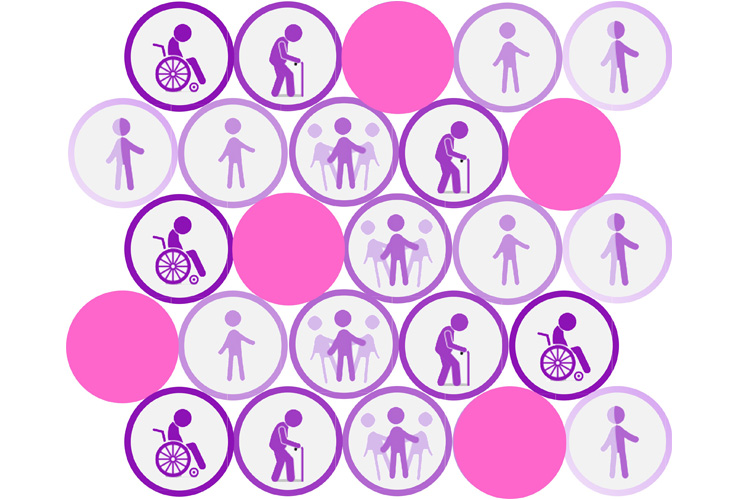
従来、Parkinson病(PD)の臨床重症度の評価にはHoehn and Yahr(H&Y)ステージングが用いられてきました。近年、αシヌクレイン(αS)病理で定義される神経疾患群を神経αシヌクレイン病(neuronal αS disease, NSD)と呼び、髄液αSやdopamine transporter imaging、非運動症状などのバイオマーカーを取り入れ、遺伝的リスク段階から重度障害に至るまでの0~6段階で病態進行を表したNSD-ISS(NSD-integrated staging system)が提案されています。
紹介する論文はParkinson’s progression markers initiativeのPD、前駆期PD、健常を対象とした5年間の縦断研究です。ベースラインではNSD-ISSステージ2Bが24%、ステージ3が56%、ステージ4が13%で、5年後にはそれぞれ11%、50%、34%となり進行が確認されました。臨床的PD発症といえるステージ2Bから3への移行は運動機能障害(95%)が主因であり、ステージ3から4では非運動症状(46%)が関与し、ステージ4から5では複数の障害が影響していました。Kaplan–Meier解析では、ステージ2Bからの進行中央値は約1.2年、ステージ3では約5年、ステージ4では約10年と段階に応じた進行速度が示され、NSD-ISSはH&Yステージングと比べ、早期の機能障害をより感度高く検出可能であると述べています。
Movement disorder societyのプレジデントだったCico先生は、バイオマーカーを用いたステージングは有望だが、現時点では予後や進行予測の妥当性が不十分のため臨床導入は時期尚早と述べていました。H&Yステージングの限界はよく知られていますが、臨床的に簡便で国際的に通用するという強みがあり、拙速に放棄するべきではないとも力を込めて仰います。無症候者に前駆期PDと病名が付く、逆に症候者に陰性結果がでるなど、まだ懸念が残ることから生物学的新基準は当面研究利用に限定すべきとしています。今回の論文はとても重要な観察を報告していて、PD研究の進歩にも貢献するものです。一方、懸念はまだ残っていて、Cico先生の洞察の通り今後も注意が必要と感じます。
文献
1. Simuni T, et al. Neuronal α-Synuclein Disease Stage Progression over 5 Years. Mov Disord. 2025;40(7):1318-1330. doi: 10.1002/mds.30191.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40302527/
2. Cardoso F, et al. A Statement of the MDS on Biological Definition, Staging, and Classification of Parkinson’s Disease. Mov Disord. 2024;39(2):259-266. doi: 10.1002/mds.29683.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38093469/
文責:まえちゃん